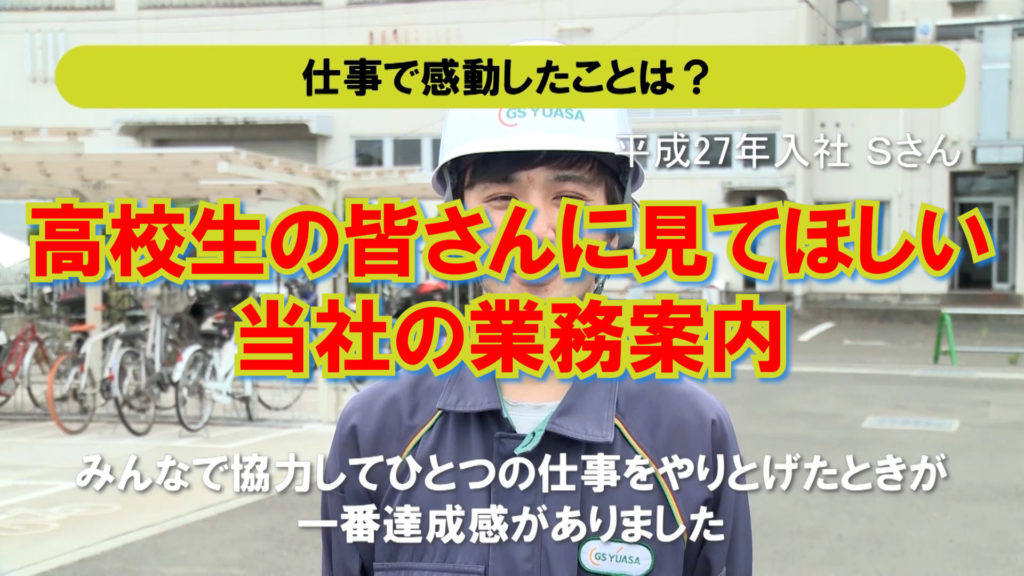音が出る電化製品はすべてトランジスタのお陰

トランジスタの役割は信号の増幅と電気回路のオフ/オンを切り替えることです。
前回お伝えしたように、最初のトランジスタは長距離電話網のために開発されました。当時の電話システムでは、音声信号を増幅する装置として真空管が使われていましたが、寿命が短く故障も多かったため、真空管よりも安定していて真空管よりも寿命が長い部品として、ベル研究所で発明されたものです。民生用としては、補聴器として初めて製品化されました。
「信号の増幅」と書くと、何やら難しそうでイメージできませんが、電話線や電波を通して波の状態で伝わってくる音声信号を変換したり、パワーアップさせてより遠くまで伝えたり、人の耳に聞こえる状態まで大きくしたりするのが元々の目的でした。
つまり、通電して音が出る装置はすべてトランジスタのお陰で成り立っていると言えます。大きな音を出すためのマイクや拡声器だけでなく、電話、ラジオ、レコードプレーヤー、テレビ、ラジカセ、ステレオアンプなど、昔ながらの”音を出す装置”には必ずトランジスタが使われているわけです。
ただし、エレキギターのアンプに関しては、音色や音の変化にこだわり、トランジスタをつかったものよりも真空管のアンプを好む人が大勢いますし、深みのある音が出るハモンドオルガンは、真空管式電子オルガンとして今も健在です。
そもそもトランジスタの増幅とは?
 音の増幅に使われた初期のトランジスタをバイポーラトランジスタと呼ばれます。世間で一般的にトランジスタと言う場合は、こちらを指すことがほとんどです。
音の増幅に使われた初期のトランジスタをバイポーラトランジスタと呼ばれます。世間で一般的にトランジスタと言う場合は、こちらを指すことがほとんどです。
バイポーラトランジスタは、そのままでは電気を通さない純度の高い半導体に、ほんの少しだけ異物を混ぜて帯電させた2種類の物質をサンドイッチ状に接合したものです。
プラスの電気を帯びたほうをP型(positive)、マイナスの電気を帯びた方をN型(negative)と呼び、PNPの形にサンドイッチしたものと、NPNの形にサンドイッチしたものの2通りあり、この2つは電気の方向が逆になります。P型の半導体とN型の半導体をこの形で接合して、図のように電源が二つある大小2系統の回路をつくると電子が独特の動きをするため、その振る舞いを利用して信号を増幅させるものです。※詳しくは冒頭の動画をご覧ください。

そのため、増幅といっても、トランジスタを通過した信号が単純にそのまま倍増されるわけではなく、電圧の小さいほうの回路で電圧の大きいほうの回路がコントロールし、少ない電気で大きな電源を持った回路を制御するしくみです。
このしくみでは、小さな回路の電源をOFFにすると大きな回路にも電源が流れないため、物理的な端子を利用しなくても電源のオフ/オンが可能になります。そのためトランジスタはスイッチ(組み合わせた回路の切り替え等)にもつかわれます。
進化したトランジスタ

トランジスタの材料には当初、ゲルマニウムが使われていましたが、ゲルマニウムは約80°C程度でこわれてしまうという欠点があったため、今では、そのほとんどが高温にも耐えられるシリコン製になっています。
この方法でトランジスタがきちんと想定通りに機能するためには、非常に純度の高いシリコンが必要になります。そのため高度に精製した単結晶をつくる技術が発達し、それと共にトランジスタもどんどん進化していきました。
やがて、回路に取り付けるパーツであったトランジスタは、プリント基板の中につくられたり、集積回路としてひとつの半導体チップの中に大量に投入されて、今ではスマートフォンのようにコンパクトな装置でも、膨大な数のトランジスタが使われるようになりました。
またトランジスタはPCの普及や家電のデジタル化に伴い、スイッチング(回路のオン・オフの切り替え)の役割も大きく重視されるようになりました。
以下はラジオの内部の写真の比較です。初期のラジオの内部は様々なパーツがところせましと並んでいますが、現在のラジオはそれらが昔とは違った形で組み込まれています。ですが、素子に変わった各パーツの数は昔のラジオよりもはるかに多くなっており、その分だけ機能も品質も飛躍的に向上しているのは言うまでもありません。(写真左:1959年製ソニーラジオ、右:1991年製ソニーラジオ)