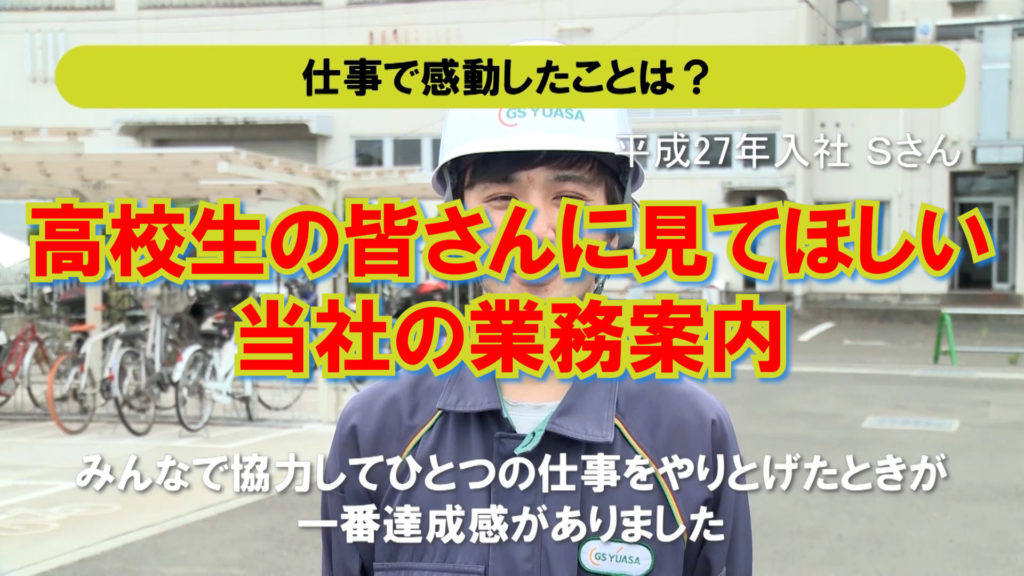1857年(安政4年) 磐城国にて生まれる。幼名 六三(ろくぞう)
1869年(明治2年) 兄と共に藩校に入学/12歳前後
1871年(明治4年) 藩命により慶応義塾で学ぶ/14歳前後
1874年(明治7年) 電信修技校に入学/17歳前後
1875年(明治8年) 工学寮にも通学、エアトンに指示/18歳前後
1888年(明治21年) 田中製作所に移る、日本最初の火災報知器製作/31歳前後
1889年(明治22年) 渡米。ウェスタンエレクトリック社に入る/32歳前後
1890年(明治23年) 帰国。三吉電機工場に入る/33歳前後
1891年(明治24年) 「電気之友」発行/34歳前後
1896年(明治29年) 電友社を開設/39歳前後
1913年(大正2年) 釜石電燈株式会社の社長となる/56歳前後
1921年(大正10年) 合資会社電気之友社として電気関連書籍刊行/64歳前後
1940年(昭和15年) 死去 /83歳
(出典:福島民報「ふくしま人 加藤木重教(藤井典子)」)
福島県出身の電気技術者・実業家です

このシリーズは今回が最終回となります。第一回の高柳健次郎を除き、主に初期の電気技術に貢献してきた明治時代の人物をご紹介してきましたが、出身地を見ると残念ながら完全に西高東低です。。。
| ①高柳健次郎 静岡 | ②藤山常一 佐賀 | ③中野初子 佐賀 |
| ④藤岡 市助 山口 | ⑤浅野応輔 岡山 | ⑥志田林三郎 佐賀 |
| ⑦エアトン イギリス | ⑧初代島津源蔵 京都 | ⑨二代目島津源蔵 京都 |
| ⑩屋井先蔵 新潟 | ⑪田中久重 福岡 | ⑫三吉正一 山口 |
| ⑬沖牙太郎 広島 | ⑭石丸安世 佐賀 |
そこで最終回は福島県出身の加藤木重教(かとうぎ しげのり)を取り上げたいと思います。
加藤木重教は安政4年に生まれ昭和の初めまで電気事業に貢献した技術者です。日本初の火災報知器や外国の模倣ではない独自の設計できんちゃく型電話機を発明した人物と言われており、後年は電友社を設立して電灯工事、電機輸入事業などのほか、日本初の電気雑誌『電気之友』を創刊した実業家でもあります。
加藤木は柔道指南として磐城平(現:福島県いわき市)から三春藩(現:福島県三春町)に招へいされた加藤木直親(なおちか)の次男で、家柄としては身分が低かったため本来は藩校で学べる立場ではありませんでしたが、明治維新による身分制度の撤廃により兄と共に藩校に入学し、その後、藩の洋学修業者に選ばれて藩命で慶応義塾に学びました。
加藤木はそこから電信修技校(逓信省所管の部内職員訓練機関)に入っているため、すでに電信技術官としての進路を選択していたと思われます。電信修技校で学びながら同時に工部大学校(工部省の技術者養成機関)の聴講生として電信科のウィリアム・エアトンにも指導を受けていた加藤木でしたが、西南戦争による技術者不足の影響で聴講は中止となってしまいました。
1887年(明治10年)仙台出張を命じられた加藤木は技官として仙台に赴任し、21歳から25歳までイギリス人技術者チールの指導の下で東北各地の電信線新設工事に従事しました。
田中久重の田中製作所でお金を溜め渡米

帰京後は逓信省の電話研究主任としてアメリカから輸入したエジソンの電話機の分解研究などを行っていた加藤木でしたが、やがて渡米して本場の技術を学びたいと思うようになりました。そこで退職を申し出ても「必要な人材だから」という理由で却下され、そのうえ費用の目途さえ付きません。すると上官の志田林三郎が田中久重の田中製作所を紹介するというのです。
「田中製作所ではいま警察用非常報知器の製作に取り掛かっており、設計と監督の適任電気技師がおらず困っている。先方でも相応の待遇を準備すると言っている。決して悪いようにはしないから助けてやって欲しい。」
迷いながらも加藤木は「そこでお金を溜めたら渡米費用に充てられる」と判断し、逓信省を辞職して田中製作所に入りました。
そして一通り責任を果たしたあと、翌年の1889年(明治22年)に弟と共に渡米しました。ちなみに田中製作所を退職するとき、所長の田中久重は「まだ完了していない」として承服しませんでしたが、入社時の約束事であったため加藤木は退職。そのため田中所長からは一言の挨拶もなかったそうです。
さらに余談ですがこのとき渡米に同行した実弟 勝沼富造(かつぬまとみぞう)はその後ハワイに移住し、福島県からのハワイ移民に深く関わったため「福島県移民の父」と呼ばれて、国内よりも現地でよく知られているそうです。
「もしもし」の考案者といわれていますが・・・
 加藤木の渡米期間はそれほど長くはなく、記録では翌年に帰国したようです。滞在中は偶然出会った歯科医の紹介でウェスタンエレクトリック社ニューヨーク工場に見習いとして入り、そこで技術を学びながら、電話機や交換機の関連会社を見学したり、講演会に出向いたりしたようです。
加藤木の渡米期間はそれほど長くはなく、記録では翌年に帰国したようです。滞在中は偶然出会った歯科医の紹介でウェスタンエレクトリック社ニューヨーク工場に見習いとして入り、そこで技術を学びながら、電話機や交換機の関連会社を見学したり、講演会に出向いたりしたようです。
帰国後の加藤木は三吉電機工場や深川電燈株式会社に技師として約7年間勤務し、その後、電友社を設立して自分の事業を開始しました。
そんな加藤木がなぜ「もしもしの考案者」と言われているのか、実はネット上には決め手となる出典が見つかりません。
ただ、国会図書館のレファレンス協同データベースでは、質問者に対して「日本語源辞典(日本文芸社)1981.7」に記載があると回答されていますので、それが唯一の手がかりかもしれません。同サイトの回答を以下に引用します。
『日本語源辞典』の、「もしもし」の項目によれば、「もし」は「申し」が略されたもの。そこで、「もしもし」は、「申し申し」の詰まったもの。電話の「モシモシ」は、明治23年、電話が日本に初めて出来た時、アメリカに研究に行った、加藤木氏が「ハロー」に代わるものとして考えついたもの、とある。『語源海』には言葉の変化、用例などで、より詳しい記述がある。他の語源辞典にも、同様の記述あり。
記録魔だった加藤木の自伝にもそれについての記載は見当たりませんが、自伝には
「電話交換局を一覧し初めて妙齢のあめりか女子オペレーターのハローハローの美声を聞くを得たり」「未来の電話交換機はテーブルの形となり大きさもその半分になり6人のオペレーターが向かい合ってハロハロと云うに至るならん」
という記述があるので、何らかの呼びかけの言葉を二回繰り返すのがあちら流という認識はあったようです。
ご参考までにこちらのサイトから以下も引用します。
1890年(明治23年)12月16日に東京の電話交換が始まった。それに先だって電話交換の交換実験が行われた際の説明書きには
『ここにおいて受容者は、聴音器を両耳にあて、器械の中央に突出する筒先を口にあて、まず「おいおい」 と呼びにて用意を問い合わせ「おいおい」の声を発して注意し、先方よりの承諾の挨拶あるを聴音器にて聞き取り、それより用談に入るなり』
とあるので、一番最初の問いかけの言葉は「おいおい」だった。当時、電話を持っている人は高級官僚や実業家などの偉い人ばかりだったので、このような偉そうな挨拶になったのかも知れない。ちなみに一番最初の電話帳には「渋沢栄一・158番」「大隈重信・177番」などの名前が掲載されている。
この当時「おいおい」に対しての受け手の応答は「ハイ、ヨゴザンス」に決定されていた。 もしもしとは「申す申す」が変化して出来た言葉だが、当初は男は「おいおい」女は「もしもし」だったらしい。 「もしもし」に統一されたのは明治35年頃と言われている。
この「もしもし」を考案したのは、電話を日本で設置する際に 研修ということで、明治23年にアメリカに渡った加藤木重教だと云われている。その時、アメリカの電話では「ハロー/Hello」と言う言葉を使っていたが、この言葉を説明する日本語がどうも判らない。そこで、「もしもし」という言葉を必死に考え出したものが、現在まで続いている。
電友社の貴重な書籍群が最大の功績

日本で最初の電気雑誌「電気之友」を発刊した加藤木は、電気に関する書籍を電友社から多数上梓しており、ネット上にはそれらを出典とする電気関連の歴史資料や研究論文が非常に多くアップされています。
また自伝の『重教七十年の旅』ではこのシリーズに登場した当時の多くの関係者たちとの出会いやエピソードなどが生き生きと記され、様々な経緯を知ることができます。
画期的な発明をしたわけでもなく、著名な事業を行ったわけでもありませんが、電話通信の将来性を見越して知識や技術の共有を重視した加藤木重教の最大の功績は、まさにこれらの書籍を後世に残したことなのかもしれません。
(ミカドONLINE編集部)
参考/参照記事 もしもしの起源 ふくしま人「電信技術者 加藤木重教」(画像) 明治期、ホノルルの名物男・勝沼富造(福島県三春) 明治日本における初期電気技術者の分析(PDF) 重教七十年の旅. 前編(国立国会図書館デジタルコレクション) など