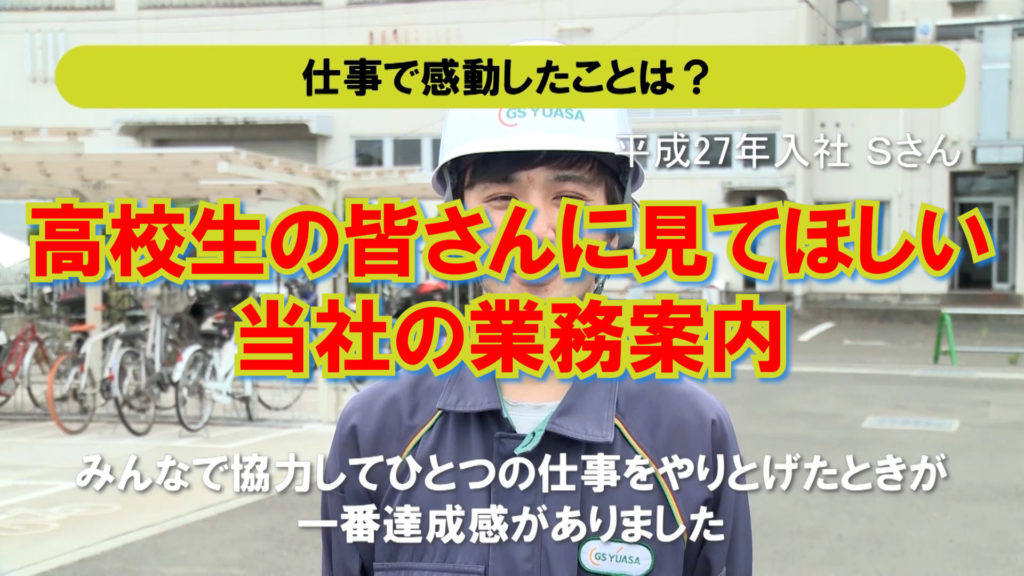前回は鉛蓄電池の分類について書きました。今回は鉛の開放型蓄電池について解説をしていきます。
前回は鉛蓄電池の分類について書きました。今回は鉛の開放型蓄電池について解説をしていきます。
鉛開放型蓄電池の新規のニーズはなくなりつつあります
以下は鉛蓄電池の分類です。
| 構造 | 極板構造 | 形式(※) | 放電性能 | 期待寿命 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開放型 (=ベント型 =液式) |
開放形 | クラッド式 | CS – □ | 標準 | 10~14年 |
| ペースト式 | PS – □ | 標準 | 8~12年 | ||
| HS – □ | 高率放電 | 5~7年 | |||
| 触媒栓式開放形 | クラッド式 | CS – □E | 標準 | 10~14年 | |
| ペースト式 | PS – □E | 標準 | 8~12年 | ||
| HS – □E | 高率放電 | 5~7年 | |||
| 密閉型 (=シールド形 =制御弁式 ) |
ペースト式 (負極吸収式) |
HSE – □ | 高率放電 | 8~12年 | |
| MSE – □ | 高率放電 | 5~7年 | |||

産業用の鉛開放型電池はベント型、液式などとも呼ばれ、水の電気分解によって発生した酸素や水素ガスを逃がすための通気孔があることや、失われた水分を補充するために定期的な補水が必要であることなどが特徴です。そのため水分の減り具合がわかりやすいように筐体が透明になっています。
CSやHSといった蓄電池の形式はJISで定められた大きさを表す規格なので各社共通です。形式が同じであれば大きさが同じなのでどのメーカーの蓄電池でも交換可能です。
開放型の鉛電池は初期の頃からスタイルが変わらない昔ながらの蓄電池ですが、現在では密閉型(シール型)に切り替わっていることが多く、新規での導入はほとんどありません。現在でも発電機の始動用として残っているものはいくらかありますが、それも今後は密閉型に切り替わっていくでしょう。
クラッド式(CS)とペースト式(HS)の用途の違いは?

開放型の鉛蓄電池にはクラッド式とペースト式の2種類がありますが、この二つの違いは極板の構造の違いです。
クラッド式はガラス繊維をチューブ状に編み上げて焼き固め、その中に極板活物質である鉛粉を充填したものです。このチューブを並べたものが正極板として使用されています。
ペースト式は格子体とよばれる極板の骨組みにペースト状にした活物質(鉛化合物)を塗り込んで極板にしたもので、正極と負極両方に使用されています。
極板の違いは一度に流れる電流の大きさを左右します。クラッド式よりもペースト式のほうが電解液に接している面積が広いので、いっきに大電流を得ることができます。そのためペースト式は瞬間的に大きな電気を必要とする非常用電源や無停電電源装置(UPS)などに使用されています。
同等の電流は密閉型でも出せますが、開放型よりも価格が高くなるため、予算的な都合で開放型をご希望されるお客様もいらっしゃいました。
クラッド式は構造的にそこまでの大電流は得られませんが、クラッド式は寿命が長いため瞬時放電の必要がない場所で使用されており、具体的には電話交換機用や大きな電流を必要としない設備のバックアップ用に使われています。また振動や衝撃にも耐性があるため、建築現場の機器等のバックアップに使用される鉛蓄電池も一部にはあるようです。
触媒栓(しょくばいせん)とは?
 触媒栓とは、触媒栓式開放型の鉛蓄電池に取り付けられている部品です。
触媒栓とは、触媒栓式開放型の鉛蓄電池に取り付けられている部品です。
鉛開放型蓄電池では電解液中の水分が電気分解され、酸素・水素ガスが発生しますが、単に混ぜ合わすだけでは水に戻すことはできません。
この混合気体に触媒を少量介在させると急激に反応が進行し、反応熱を伴って水蒸気を生成します。生成した水蒸気は、冷却されて水滴となり電解液中に還流されるため、電解液の減るスピードが緩やかになり、精製水の補充頻度を少なくすることが出来ます。なお、触媒栓も定期的な交換が必要であり、使用目安は5年とされています。
現在、新設される装置で触媒栓式の鉛蓄電池(開放型)がつかわれることはほとんどありませんが、過去に設置された蓄電池が多数ありますので今も目にする機会は多いです。触媒栓式開放型の鉛蓄電池は最初からセットになっている型式のものを選ぶ形になります。
(参考動画:触媒栓の交換を会社の敷地で再現してもらいました)
更新需要が今もあります
ところで分類表に掲載のあるPS型の電池ですが、機能的にはクラッド型とペースト型の中間のような位置づけです。独自に開発された経緯のある蓄電池のためあまり一般的ではありませんが、この電池は鉄道会社に採用されて、現在は踏切を動作させるための電池として使われています。
開放型の蓄電池が新規で使われることは非常に少なくなりました。ただし、発電機などでは今でもHS型などが最初から搭載されている場合もあるようです。
開放型の鉛蓄電池は価格が安いことから更新需要はまだありますが、実際には期限切れに気づかずにそのまま使われているようなケースもよくあります。皆さん、この機会にぜひご確認ください。
(ミカドONLINE編集部)
出典/参考記事: 日本電気技術者協会 など